不動産を売却して利益がでると税金がかかります。ここでは、売却した時の利益にかかる譲渡所得税等の仕組みと制度、計算方法などについて細かく解説します。
また、税金を大幅に減らすことができる特例のほか、売却の現場で起こる困ったときの対応方法もご説明します。
1. 売却時にかかる税金の仕組みと概要
不動産を売却した時の利益にかかる税金には、所得税(復興税含む)と住民税の2種類があります(両方を合わせて譲渡所得税等と言います)。
税金の申告・納税の時期と方法
所得税と住民税では、納税時期が異なります。
まず、納税が必要な場合と特別控除などの特例を受ける場合には確定申告が必要です。確定申告は、物件を売却した翌年の2月16日~3月15日に行い、その申告の際に所得税を納税します。
物件の売却で利益が出ていなくて譲渡所得税等が無く、特例も受けない場合は、確定申告は不要です。
住民税については、所得税の確定申告に基づき計算されますから、個別の申告は不要です。後で市区町村から納税通知書が送られてきますから、納税はそちらに基づいて支払います。
譲渡所得税等の金額の計算方法
税額は、物件を売却した収入から、その物件を購入した時にかかった金額、今回の売却にかかった費用、特例を受けた場合の特別控除額を差し引き、税率をかけて計算します。
譲渡所得税等 =( 売却収入 - 物件の取得費 - 売却費用 - 特別控除 )× 税率
売却収入の額は、物件の売却価格に固都税の清算金を加算した金額です。
税率は、物件の所有期間により異なります。
自宅の売却では利益3000万円まで税金が免除される
自分で住んでいる家、いわゆるマイホームの売却では、3,000万円の特別控除という特例の適用を受けられることが多く、その場合、売却益が3,000万円以下であれば譲渡所得税等はかかりません。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
これは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例です。
以前に住んでいた家の場合には、住まなくなった日から3年目を経過する日の属する年の12月31日までに売ったものに限られます。また、途中で賃貸用として利用していても適用できます。
なお、前年、前々年において居住用財産の特例の適用を受けている場合は使えないほか、一定の親族・同族会社等への売却の場合には使えません。
ただし、特例の適用を受けるには、申告が必要です。納税は無くても申告が必要ということに注意してください。
*参考:国税庁ホームページ No.3302 マイホームを売ったときの特例
建物共有の時は複数の人に適用できる
同居する夫婦や親子等で建物を共有している場合、売却する共有者ごとに最高3,000万円の控除が受けられます。例えば、夫婦で共有の場合、夫3,000万円、妻3,000万円なので、最高6,000万円までの控除を受けることが可能です。
ただし、それぞれ1人ごとに最高3,000万円ですので、夫5,000万円+妻1,000万円という形での控除は受けられません。
また、土地だけを所有していて、建物の持分を所有していない、という人はこの特例を受けることができません。
自宅を買い換える時の特例
マイホームを、対象期間内に売却し、売った年の前年から翌年までの3年の間に代わりのマイホームに買い換えたときに、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる特例です。(譲渡益が非課税となるわけではありません。)
居住期間・所有期間が共に10年を超えるものであることや売却代金が1億円以下であることなどの条件があります。
なお、この特例は、3000万円の特別控除と同時に適用することはできません。買い換えの特例と3000万円の特別控除のどちらが有利か、というのはケース毎に異なりますが、3000万円の特別控除を受けても譲渡所得税等が多額になる場合には、買い換えの特例の利用を検討すると良いでしょう。
*参考:国税庁ホームページ No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例
相続した空き家の売却でも3000万円の控除がある
相続(または遺贈)で亡くなった方(被相続人)の自宅を取得した場合で、以下の条件に当てはまる場合は、譲渡所得の金額から最高3,000万円までの控除を受けることができます。
<建物の条件>
- 昭和56年5月31日以前に建築された建物
- 区分所有建物登記がされていない
- 相続の直前に被相続人以外に居住をしていなかった
- 一定の耐震基準を満たすもの、又は解体して売ること
<売却の条件>
- 相続後、事業、貸付け、居住に使われていたことがない
- 相続があった日から3年目の年の12月31日までに売ること
- 売却代金が1億円以下
そのほか、細かい条件等もありますので、詳しくは税務署または税理士にご確認ください。
*参考:国税庁ホームページ No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
2. 物件を所有していた期間で税率が異なる
税率は、短期譲渡と長期譲渡の2種類に分かれていて、不動産の所有期間によって変わります。
短期譲渡と長期譲渡
短期間での転売など投機を防止する観点から、所有期間が短いと高い税率が適用されます。
短期譲渡(5年以下):39.63%
長期譲渡(5年超) :20.315%
この税率には、所得税・復興税・住民税の3つが含まれていて、短期譲渡は、所得税30%+復興税0.63%+住民税9%、長期譲渡は、所得税15%+復興税0.315%+住民税5%の合計になっています。
所有期間は売却した年の1月1日時点が基準
どちらに該当するかは、譲渡した年の1月1日の時点で、その不動産の所有期間が満5年以下か、5年超か、で決まります。
例えば、2016年中に購入した不動産の場合、2017年1月1日時点がスタートになり、
→ ①2018.1.1 → ②2019.1.1 → ③2020.1.1 → ④2021.1.1 → ⑤2022.1.1
となって、2021年中に売却すると短期譲渡になり、2022年以降の売却ならば5年超で長期譲渡になります。
不動産の所有者に課せられる固定資産税・都市計画税も、1月1日の所有者に納税義務があるように、不動産の税金は1月1日の所有を基準にしている、と考えると分かりやすいでしょう。
所有期間10年超の軽減税率の特例
また、所有期間が10年を超えると、譲渡所得の6,000万円までの部分について、税率の軽減の特例が適用できます。
10年超所有の軽減税率:14.21%
※所得税10%+復興税0.21%+住民税4%の合計
ただし、対象は、居住用家屋とその敷地のみで、3000万円特別控除を受けている場合に限られます。また、買換えの特例や交換の特例との併用はできません。
売却した日は、契約日と引渡し日のどっち?
不動産を購入した日(取得日)・売却した日(譲渡日)は、個人の場合には、次のどちらかを選択できます。
① 物件の引渡し日(原則)
② 売買契約の効力発生の日(売買契約の締結日)
少し細かい内容ですが、売買契約において停止条件など売買契約日に効力が発生しない条件設定がある場合、②は売買契約の締結日ではなく、実際に効力が発生した日となります。
なお、取得日を売買契約の効力発生日にして、譲渡日は不動産の引渡し日にする、ということも認められています。ただ、建築中の分譲マンションや請負建築での取得など、売買契約の時点で完成していない不動産の場合には、引渡しを受けた日が取得日になります。
3. 譲渡費用
譲渡費用は、不動産を売るために直接かかった費用のことです。
主に以下の4つがあります(マンションの場合は、上2つ)。
- 売却の仲介手数料
- 印紙税
- 建物の解体費用
- 測量費用
上記のほか、既に締結している売買契約を解除する際の違約金や賃借人の立ち退き料などを含めることができます。なお、修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理のためにかかった費用は対象となりません。
同じ費用でも、ケースによって譲渡費用に該当する場合、しない場合があります。詳しく知りたい場合は、下記をご参照ください。
*参考:国税庁ホームページ No.3255 譲渡費用となるもの
4. 取得費の内容と取得費が分からない時の対応方法
取得費は、その不動産を購入(取得)するのにかかった費用のことです。
取得費の内容
取得費には、不動産の購入代金、購入手数料のほか設備費や改良費などが含まれます。なお、建物の取得費は、減価償却費相当額を差し引いた金額となります。
取得費 = 不動産の購入代金 + 購入手数料等 + リフォーム代等 - 減価償却費
購入手数料等 = 購入時の仲介手数料・印紙税・登記費用(登録免許税含む)・不動産取得税など
※事業所得などの必要経費に算入されたものは含まれません。
*参考:国税庁ホームページ No.3252 取得費となるもの
取得費は、購入時の売買契約書や売買代金の支払いの領収書などを根拠資料とします。購入時の預金通帳の記録や物件のチラシやパンフレット、売主や仲介業者の記録なども参考とすることができます。
売買契約書を紛失してしまった場合の取得費
昔に購入した場合や相続で物件を引き継いだ場合には、購入時の売買契約書が無くなっていて、その物件をいくらで購入したのか分からないこともよくあります。
このような場合には、以下の方法で対応します。
売却価格の5%を取得費と見なす方法(概算取得費)
概算取得費は、実際の購入価格にかかわらず「売却価格の5%で取得したと見なす」ことができるという制度です。
例えば、土地を5,000万円で売却する場合、その土地を、いつ・いくらで購入したのかに関係なく、取得費を250万円( 5,000万円 × 5% )として譲渡所得税等を計算することができます。
先祖代々の土地や、戦前に購入した土地など、売買価格が分からなかったり、売却価格の5%未満の価格で購入した物件の場合には、この概算取得費を用います。
概算取得費を採用した場合、取得費は売却価格の5%ですから、売却価格の大部分が利益に該当することになり、3000万円の特別控除などの特例の適用が無ければ、長期譲渡の場合でも売買価格の18~19%ほどが税金となります。
しかし、売却物件の購入時期が昭和50年代以降の場合には、売却価格の5%を大きく超える価格で購入している可能性が高く、概算取得費を用いると過大に税金を納めることになる可能性があります。
一度、概算取得費で税の申告をすると、後で別の取得費で申告しなおす更正の手続きは行えないため、概算取得費よりも高い価格で購入した可能性が高い場合には、まずは、実際に購入した価格の分かる資料を探すことが重要です。
売買契約書や領収書等がない場合は、原則として概算取得費を採用する
売買契約書や売買代金の領収書など、売買代金が分かる資料が無い場合には、原則として、概算取得費を採用することになります。
しかし、以下のような証拠資料をできるだけ用意して、信憑性を高めることによって、実額取得費として認められる場合もあるそうです。
- 通帳など購入時の出金が分かる資料
- ローン償還表など住宅ローンの返済が分かる資料
- 登記簿など抵当権の設定金額が分かる資料
- 販売のパンフレットなど購入時の価格が記載されている資料
上記に加えて、市街地価格指数や標準的な建築価額表等の統計データを基に価格を算出して補完することも有用だそうです。(公益財団法人日本税務研究センターより引用)
抵当権の設定額だけが分かる場合の対応
よく見られるのは、登記簿に購入時の抵当権の金額が記録されているが、売買契約書などの証拠資料が紛失してしまっている、というケースです。
このケースについて国税局電話相談センターに確認してみたところ、以下のような回答でした。
「① 不動産会社や金融機関から売買契約書の写しをもらう、② 支払い金額が分かる通帳を用意する、のどちらかで対応してください。これらが用意できない場合、売却価格の5%で取得したと見なす概算取得費での計算になります。」
この回答に対して、もう少し食い下がってみたところ、「個別のケースについては、管轄の税務署に個別相談をして下さい。」とのコメントがありました。
市街地価格指数で取得費を推計する方法
上記のケースについて、不動産売買に詳しい税理士先生に改めて確認したところ、以下の回答をもらえました。
- 認定されるかは税務署の判断になりますが、売買契約書でなくても、当時のチラシなど売買価格の裏付けがあれば、証拠になるので取っておいてください。
- 抵当権設定のみだと取得費用と見なされない可能性もあるので、地価変動などを裏付け資料とするのが良いでしょう。地価変動の裏付け資料としては、市街地価格指数で妥当性を確認した申述書を提出する方法があります。
市街地価格指数は、昭和30年代からの宅地価格の変動を見ることができる指数で、一般社団法人 不動産研究所が年2回調査を行い公表しています。
なお、抵当権の設定等もされておらず、購入価格が不明の場合にも、市街地価格指数を用いて取得費を推計して認められる事例があるそうです。ただし、認められるには、諸々の条件がそろっている必要があるそうですから、事前に税理士の先生に相談して確認しておく必要があるでしょう。
5. 建物の取得費は減価償却費を考慮する
建物の取得費については、取得した時の金額等に経年劣化による価値の低下を考慮する必要があります。この経年劣化による価値の低下を減価償却と呼びます。
減価償却費の計算方法
建物の減価償却費は以下の式で計算します。
減価償却費 = 建物購入代金 × 0.9 × 償却率 × 経過年数
償却率は非事業用(自宅・セカンドハウス)と事業用(賃貸用)で異なります。
自己居住用物件の減価償却費
建物の構造によって、償却率は異なります。償却率は下記の通りです。
- 木造:0.031
- (鉄骨)鉄筋コンクリート:0.015
- 金属造(骨格材の肉厚が3mm以下):0.036
- 金属造(骨格材の肉厚が3~4mm以下):0.025
- 木造モルタル:0.034
経過年数は端数が6ヶ月以上のときは1年とし、6ヶ月未満のときは切り捨てます。
賃貸用物件の減価償却費
賃貸用など事業用の物件については、毎年の減価償却額の合計となります。
賃貸用:耐用年数47年・償却率0.022
賃貸用(H9.12.31までに取得したもの):耐用年数60年・償却率0.017
建物の購入代金が分からない時
売買契約書に、土地と建物金額が分けて記載されていれば良いのですが、土地と建物を合わせての価格しか書いていないことも良くあります。
個人が売主となる戸建て住宅やマンションの売買契約では、土地と建物を分けることは行いませんし、事業者が売主の場合でも、マンションでは土地と建物は一体として取り扱われるので、建物だけの購入代金が分からないことが多いのが一般的です。
購入時の売買契約書に消費税額が記載されている場合
事業者が売主となった物件を購入している時には、本体価格と消費税の額が別に記載されています。
土地には消費税がかからないため、消費税額をその時の消費税率で割り戻せば、建物の金額が分かります。
建物の購入代金 = 消費税額 ÷ 消費税率 + 消費税額
<購入年月と消費税率>
- H1(1989).4.1~H9.3.31 :3%
- H9(1997).4.1~H26.3.31 :5%
- H26(2014).4.1~R1.9.30 :8%
- R1(2019).10.1~ :10%
購入時の売買契約書に消費税額がない場合
売主が一般の個人などで、消費税の課税事業者でない場合には、消費税がかかっていませんから、消費税額から建物の価格を逆算することはできません。
その場合、建物の購入代金の計算は、複数の方法から選ぶことができます。ここでは代表的な2つの方法を説明します。
① 建物の標準的な建築価額表による方法
② 固定資産税評価額の比率で按分する方法
① 建物の標準的な建築価額表による方法
建物の標準的な建築価額表の建築単価に、建物の面積を掛けて建物代金を計算する方法です。
建物の購入代金 = 該当する建築単価 × 登記の床面積
(建物の標準的な建築価額表は、こちらをご参照ください。)
<計算のやり方>
- 1)まず、登記簿で建物構造と建築年を確認します。
- 2)次に、建物の標準的な建築価額表で該当する建築単価を見つけます。
- 3)そして、その建築単価に、同じく登記簿に記載されている床面積を掛けて、建物代金を算出します。
なお、分譲マンションの場合には、その専有部分の床面積とすることができます。
② 固定資産税評価額の比率で按分する方法
固定資産税評価額の割合で、物件の購入代金を土地分と建物分に分ける方法です。
- 1)まず、評価証明書や固定資産税の課税明細書で物件の土地と建物の評価額を確認します。
- 2)次に、以下の算式で、建物代金を計算します。
建物代金 = 物件の購入代金 × 建物の評価額 ÷( 土地評価額 + 建物評価額 )
マンションの場合、土地や建物の共用部についてはマンション全体の評価額がでていますから、その場合は、そこに自分の持ち分割合を乗じて、自分の所有分の固定資産税評価額を計算します。
6. 売却で損失がでたときの特例
不動産の譲渡所得は分離課税なので、不動産の譲渡所得同士は合算できますが、給与所得や事業所得など他の所得とは損益を通算することはできません。
ただし、マイホームの売却で損が生じた場合には、その損失を他の所得と損益を通算できる特例があります。この特例では、通算を行っても控除しきれない損失の金額は、売却の年の翌年以後3年間にわたり繰り越して控除することもできます。
- ① 家を買換えた場合に譲渡損失が生じたときの特例
- ② 住宅ローンが残っている家を売却して譲渡損失が生じたときの特例
※いずれも期間の制限のある制度なので注意してください。
売却益がでた時の特例と同様、前年、前々年において居住用財産の特例の適用を受けている場合は使えないほか、一定の親族・同族会社等への売却の場合には使えません。また、譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えている必要があります。
① 家を買換えた場合に譲渡損失が生じたときの特例
家(マイホーム)を、対象期間内に売却し、売った年の前年1月1日から売却翌年12月31日までに代わりのマイホームに買い換えたときに、譲渡損失を他の所得との損益通算できる特例です。
買換資産(新しい家)を取得した年の12月31日において、買換資産について償還期間10年以上の住宅ローンを有することなどの条件があります。
*参考:国税庁ホームページ No.3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき
② 住宅ローンが残っている家を売却して譲渡損失が生じたときの特例
家(マイホーム)を、対象期間内に売却し、その売却価格が売却契約日の前日における住宅ローンの残高よりも低い場合に、その差額を損失として他の所得と損益通算できる特例です。
マイホームの売却の契約日の前日において、そのマイホームに償還期間10年以上の住宅ローンの残高があることなどの条件があります。
*参考:国税庁ホームページ No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき
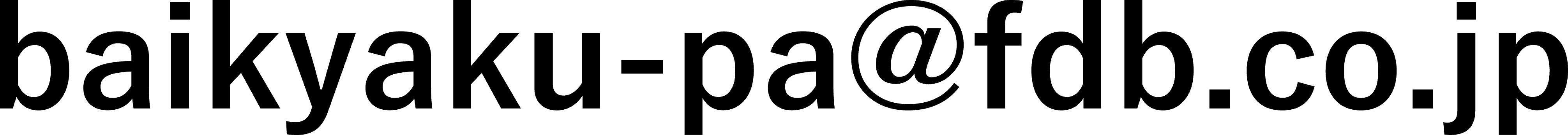 へご連絡下さい。
へご連絡下さい。